- もう60歳か!そろそろ相続について考えないと…
- 遺された家族にトラブルや迷惑をかけたくない!
- 相続対策って、いったい何をやったらいいのだろうか?
60代を迎えて「相続」について考えても、何から始めていいのかわからないですよね!
でも、大丈夫ですよ。
相続対策の基本から具体的な実践方法まで、FP(ファイナンシャル・プランナー)がわかりやすく解説します。
私は相続対策の必要性を感じ、これまでに1級FP技能士、CFP、相続手続カウンセラー、終活アドバイザーの資格を取得しました。
相続のプロが読者のみなさんへ、相続に備えて役立つ情報を出し惜しみすることなく提供します。
この記事を読むことにより、以下のメリットが得られます。
- 相続対策の基本的な知識が身につく。
- 相続税の仕組みや節税方法が理解できる。
- 家族との話し合いや専門家への相談の進め方がわかる。
相続対策を進めることは、将来への不安を取り除き、今を生きる喜びを得ることができます。また、家族との絆を深めるきっかけにもなり、何よりも安心感を得ることができます。
本記事により相続の基本を理解し、相続対策を速やかに始め、ゆとりと安心感のある老後を迎えましょう!
相続の基本事項

相続とは亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務を、法律で定められた方法に基づき相続人が引き継ぐことを指します。
相続の対象となる財産
相続の対象となるのは、現金や預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけではありません。
借金や未払いの税金といったマイナスの財産も相続対象になります。そのため、被相続人がどのような財産を持っているのか、リストアップしておくことが重要です。
相続人の範囲と順位
相続人になれるのは法律で定められた親族です。最も優先されるのは配偶者で、常に相続人になります。
配偶者以外の相続人は、以下のような順位で決まります。
1.子ども
2. 両親(子どもがいない場合)
3. 兄弟姉妹(子どもも両親もいない場合)
これらの順位を把握することで、誰が相続手続きに関わるのかを明確にできます。
法定相続分と遺言書の役割
法律では、相続財産をどのように分けるかを法定相続分として定めています。しかし、被相続人が遺言書を作成していれば、その内容が優先されます。
遺言書がある場合、相続手続きがスムーズになるだけでなく、家族間のトラブルも減少できます。
遺言書には大きく分けて以下の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言: 被相続人が手書きで作成するもの
- 公正証書遺言: 公証人が作成し、公証役場で保管するもの
- 秘密証書遺言: 内容を秘密にしたまま公証役場で手続きするもの
秘密証書遺言を作成する方は稀で、ほとんどの方が自筆証書遺言または公正証書遺言を作成しています。
相続に関する課題と準備
相続は家族間のトラブルが生じやすいテーマです。「誰が何をどれだけ受け取るのか」という問題が原因で、親族間の関係が悪化するケースも少なくありません。
また、相続税の負担や手続きの煩雑さも大きな課題です。
こうした課題に備えるためには、事前準備が欠かせません。
被相続人が元気なうちに、財産の整理や相続人との話し合い、そして遺言書の作成を進めることで、相続がスムーズに進みます。
60代から始める相続対策

日本は世界でも有数の高齢化社会を迎えています。この中で、自分の財産を次世代にスムーズに引き継ぐための相続対策がますます重要になっています。
早めに準備を始めることで、家族が将来困らない体制を整えることができます。
60代から相続対策を始める理由
元気なうちに相続対策の実施
相続対策は、心身ともに元気なうちに行うことが理想的です。
自分の意思や希望を明確に伝えられるタイミングで取り組むことで、家族への負担を減らし、スムーズな手続きができます。
家族間のトラブル防止
相続においてしばしば問題となるのが家族間でのトラブルです。意見の食い違いや遺産分割を巡る争いを防ぐためには、事前の準備と家族間の話し合いが大切です。
早めに対策を講じることで、家族全員が安心して暮らせる環境を作り出せます。
財産の把握と整理
財産内容のリスト化と評価
相続対策の第一歩は自分の財産を正確に把握することです。預貯金や不動産、株式などの資産をリスト化しましょう。
リスト化したら次は評価です。
土地は「路線価方式」または「倍率方式」が基準で、建物は「固定資産税評価額」を基本として計算します。
不動産や株式の評価額を算出するのは、大変複雑で困難ですので相続税を専門とする税理士に相談した方が賢明でしょう。
負債の確認と処理方法
財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
住宅ローンや借入金がある場合、それらを明確にして、どのように処理するのか計画を立てておくことが大切です。
負債を放置しておくと、相続人に予期せぬ負担を与える可能性があります。
相続トラブル防止のための具体策
家族間での話し合いの場の設定
相続に関する意見の食い違いを解消するためには、家族全員で話し合いの場を設けることが重要です。
財産情報を家族と共有することで、将来的なトラブルを回避できます。
相続財産の透明性を確保し、相続に関する家族間の信頼関係が強化され、不要な誤解を防げます。
財産分割の希望や不安点を率直に話し合い、合意形成を図りましょう。家族会議を開く際は、第三者のサポートを得るとスムーズに進むことがあります。
遺言書の作成
遺言書は、相続トラブルを防ぐための強力なツールです。法的に有効な形式で作成し、自分の意思を明確に伝えることができます。
遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが主流です。
自筆証書遺言は、誰にも見せずに自分で簡単に作成でき、費用がかからないというメリットがあります。
しかし、家庭裁判所の検認が必要なこと、内容や方式の不備で無効になる、紛失・偽造・改ざんのリスクがあるなどのデメリットがあります。
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要、方式不備で無効になる心配が少ない、紛失・改ざんのリスクが少ないなどのメリットがあります。
ただし、手数料など多額の費用がかかる、証人が必要、作成に時間がかかるなどのデメリットがあります。
財産が多い場合や相続トラブルを防ぎたい場合は、公正証書遺言の方が安心ですよね。
ただし、費用と手間がかかるので、何かほかに良い方法はないものでしょうか?
2020年にスタートした自筆証書遺言の法務局保管制度は、新たな選択肢として活用できそうです。
遺言書の内容が法的に適切かどうかは保証されませんが、家庭裁判所の検認が不要で、紛失・改ざんの心配がなく、費用が安くておすすめです。
専門家のサポート活用
相続対策をスムーズに進めるためには、専門家の力を借りるのがおすすめです。
税理士や弁護士、司法書士、FP(ファイナンシャル・プランナー)など、相続に精通した専門家に相談することで、より的確な対策が可能になります。
知っておきたい相続税の節税方法

相続税は、大切な資産を次世代に引き継ぐ際に避けて通れない課題です。効果的な節税対策を知り、賢く準備することで、家族の負担を軽減できます。
以下、具体的な節税方法について詳しく解説します。
相続税の計算方法
① 相続財産の総額を計算
被相続人の財産の総額を算出します。
対象となる財産としては、不動産(土地・建物など)、預貯金、株式・投資信託、貸付金、生命保険金などです。
控除される財産としては、生命保険金(500万円×法定相続人の数)、借金・未払い税金、葬儀費用などです。
② 基礎控除を引く
相続税には、基礎控除という非課税枠があります。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
【例】法定相続人が 妻と子2人(計3人) の場合➡ 3,000万円+600万円×3=4,800万円 が基礎控除額
相続財産の総額が 4,800万円以下なら相続税はかかりません。
③ 法定相続分で仮の相続税額を計算
基礎控除後の課税遺産総額を、法定相続分で分けたと仮定して、各人ごとの税額を計算します。
引用:相続税の速算表|No.4155 相続税の税率|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
【例】課税遺産総額が1億円、法定相続人が妻と子2人の場合
課税遺産総額を法定相続分で分ける。
妻:1/2(5,000万円)
子A:1/4(2,500万円)
子B:1/4(2,500万円)
各人ごとに相続税を計算する。
妻(5,000万円) → 5,000万円 × 20% - 200万円 = 800万円
子A(2,500万円) → 2,500万円 × 15% - 50万円 = 325万円
子B(2,500万円) → 2,500万円 × 15% - 50万円 = 325万円
仮の合計相続税額:800万円 + 325万円 + 325万円 = 1,450万円
④ 実際に相続した割合で税額を再計算
家族全体の相続財産を各相続人が実際に相続した割合に基づいて再計算します。
実際に相続した以下の金額で相続税額を算出します。
妻:6,000万円
子供A:2,000万円
子供B:2,000万円
妻の相続税額:1,450万円×6,000万円/1億円=870万円
子供Aの相続税額:1,450万円×2,000万円/1億円=290万円
子供Bの相続税額:1,450万円×2,000万円/1億円=290万円
となります。
妻の相続税額は870万円と算出されましたが、相続税の配偶者控除が適用でき相続税額は0円となります。
各種控除・特例の活用
相続税の負担を軽くするための制度を活用します。
相続税の配偶者控除
配偶者は1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い方の金額まで配偶者には相続税がかからないという制度です。
小規模宅地等の特例
一定の要件を満たす場合に宅地等の評価額を最大80%下げる軽減措置です。
生命保険の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数まで非課税となります。
結果として、
- 基礎控除以下なら相続税は0円!
- 相続税対策をするなら「配偶者控除」「生命保険」「生前贈与」などを活用すると節税ができます!
相続財産が高額になる場合は、税理士に相談するのがいいでしょう。
生前贈与と暦年課税制度の活用
暦年課税制度のメリットと注意点
暦年課税制度とは毎年一定額まで非課税で贈与できる制度です。基礎控除額は年間110万円で、この範囲内であれば贈与税がかかりません。
この制度を活用することで、長期的に資産を分散させ、相続財産を減らすことが可能です。
相続財産が減るということで、相続税対策に暦年課税を使う人も少なくありません。
ただし、毎年定期的に110万円の贈与を行って非課税枠を使い続けると、場合によっては「定期贈与」とみなされ贈与税がかかる場合もあります。
定期贈与とみなされないようにするためには「毎年違う時期に贈与する。毎年違う金額を贈与する。贈与契約書を作成する。銀行振込で贈与する」などの対策が必要でしょう。
生前贈与の効果的な活用法
生前贈与を計画的に行うことで、相続税の課税対象を大幅に減らせます。
例えば、不動産や現金を子や孫に早めに贈与することで、財産評価額を減らす効果が期待できます。
また、教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与する特例を利用することで、さらに節税を進められます。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
直系尊属(父母や祖父母)から30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与した場合に一定の要件を満たせば、1500万円までの金額が非課税になります。
参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・子育て資金を一括贈与した場合に一定の要件を満たせば、1000万円(結婚は300万円)までの金額が非課税になります。
参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産または居住用の不動産を購入するための金銭の贈与があった場合で一定の要件を満たせば、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除を受けることができます。
参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
注意すべき贈与税の課税ルール
生前贈与には贈与税がかかる場合があります。基礎控除を超える贈与額には累進税率が適用され、高額になる可能性もあります。
また、2023年(令和5年)の税制改正により、相続発生までの一定期間までの贈与を相続財産に持ち戻す「持ち戻しのルール」が3年から7年へと延長されました。
2024年(令和6年)1月1日以降に受けた贈与が対象です。
2027年(令和9年)以降に発生する相続から持ち戻し期間が加算されていき、2031年(令和13年)から持ち戻し期間は7年間となります。
ただし、延長された4年分については「総額100万円」まで、相続財産には加算されません。
引用:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
引用:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
相続時精算課税制度
制度の概要と利用条件
相続時精算課税制度は贈与時に一定額まで非課税とし、相続時にまとめて課税される仕組みです。
累計で2,500万円までの贈与が非課税となり、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与が対象です。
2023年(令和5年)税制改正によって年間110万円の基礎控除が新設されました。
この制度を利用すれば毎年110万円までの贈与分は相続時に加算されなくなりましたので、相続時精算課税制度の利便性が向上したと言えるでしょう。
引用:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
運用する際の注意点
相続時精算課税制度は一度選択すると、暦年課税制度に戻れません。
また、将来の相続税負担が一時的に増加する可能性があるため、家族全体の財産計画を慎重に立てる必要があります。
生命保険と相続税の配偶者控除の活用
生命保険金の非課税枠の活用
生命保険金は法定相続人1人あたり500万円まで非課税となります。
この非課税枠を活用すれば、まとまった資金を相続人に残しつつ、相続税の節税が可能です。特に、現金での相続対策が必要な場合に有効です。
相続税の配偶者控除を最大限に生かす方法
配偶者は相続税の配偶者控除により、法定相続分または1億6,000万円のいずれか高い金額まで相続税が非課税となります。
この控除を最大限に活用するためには、遺言書の作成や財産分割の計画が重要です。また、配偶者が安心して生活を続けられるよう、適切な財産管理も心がけましょう。
相続対策を進めるための実践ガイド
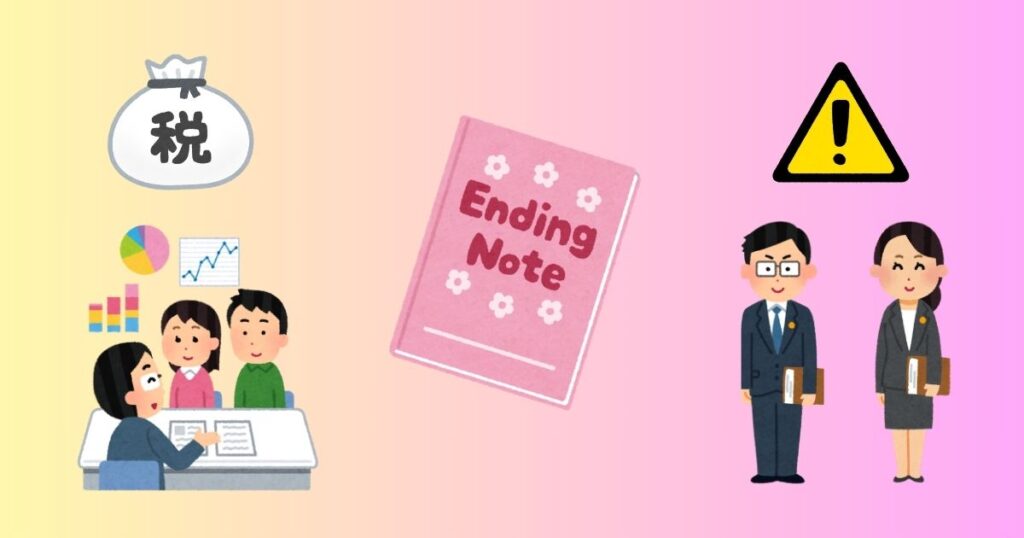
エンディングノート
相続対策の第一歩はエンディングノートの作成です。このノートは、自分の財産状況や希望を明確に記載し、家族に情報を伝える重要なツールとなります。
基本構成
エンディングノートには以下の内容を含めるのが一般的です。
- 個人情報(氏名、住所、生年月日など)
- 財産リスト(預貯金、不動産、保険、株式など)
- 遺言の有無と保管場所
- 希望する葬儀の形式や連絡先
- 家族や友人へのメッセージ
この構成を基に、自分の状況に合わせてカスタマイズしましょう。
考慮すべきポイント
エンディングノートを作成する際には、次の点に注意してください。
- 書きやすい形式を選ぶ:市販のテンプレートやデジタルツールを活用すると便利です。
- 定期的な更新:状況が変われば内容を見直す必要があります。
- 分かりやすく記載:専門用語は避け、家族が理解しやすい言葉を使いましょう。
家族への共有方法
エンディングノートを作成した後は、信頼できる家族に存在を知らせておきましょう。
家族への情報共有
- 作成したノートの保管場所を明確に伝える。
- 家族会議の場で共有し意見を聞く。
- 必要に応じて専門家にも確認してもらう。
専門家への相談のすすめ
相続対策を効果的に進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な手段です。
税理士・弁護士・司法書士・FPの役割
- 税理士:相続税の申告や節税対策において重要なアドバイスを提供します。
- 弁護士:法的トラブルを未然に防ぐための遺言書の作成や相続紛争の対応を行います。
- 司法書士:相続人調査、相続財産調査、不動産の相続登記などを行います。
- FP:資産の全体像を整理し、長期的な視点での対策を提案します。また、相続内容に応じ、パイプ役として専門の士業につないで連携して業務を行います。
専門家選びの基準と信頼関係の構築
適切な専門家を選ぶには、以下を参考にしてください。
- 実績や専門分野を確認する。
- 初回相談時に相性を見極める。
- 誠実な対応や透明性を重視する。
相続対策の長期的なサポート体制
専門家と定期的に連絡を取り合い、法律や税制の変更に対応できる柔軟な体制を築きましょう。これにより、突然の状況変化にも備えられます。
遺産相続での注意点
配偶者居住権の設定
2020年(令和2年)に導入された配偶者居住権を活用することで、配偶者が安心して住み続けることができます。
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた実家などの建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利のことです。
参考:配偶者居住権|配偶者の居住の権利|E-GOV法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_8-Se_1
納得できる遺産分割の実施
家族間のトラブルを避けるため、以下を心がけましょう。
- 生前に話し合いの場を設ける。
- 公平な分割案を検討する。
- 遺言書を作成し、意図を明確に伝える。
まとめ

60代は相続対策を始める最適な時期です。健康で判断力があるうちに、財産の把握や整理を進め、家族とのコミュニケーションを図ることができます。
相続の基本事項、60代から始める相続対策、知っておきたい相続税の節税方法、相続対策を進めるための実践ガイドなどについてご理解いただけたと思います。
元気なうちに遺言書の作成や専門家への相談を行うことで、家族間のトラブルを未然に防止し、相続の準備を円滑に進めることができます。
相続対策の基本と実践のポイントは、
- 財産のリスト化と評価
- 負債の確認と処理
- 相続税額の把握と減税対策
- 家族との信頼性の確保
- 遺言書の作成と保管
- 専門家の活用
などです。
相続は財産の分割だけでなく、家族の絆を守り、「想い」と「つながり」を次世代へ引き継ぐことが大切です。
相続対策として、財産の整理、トラブル防止、税負担軽減の準備が必要です。
財産の整理や遺言書を作成し、家族との話し合いを進め、必要により専門家への相談を始めましょう。
相続対策を早めに始めることにより、家族が安心して相続を受け入れる環境が整います。
60代は相続の準備をスタートさせる絶好の時期です。計画的に相続対策を行い、最期までやりたい夢を追い続け、安心とゆとりある素適な老後を送りましょう!
